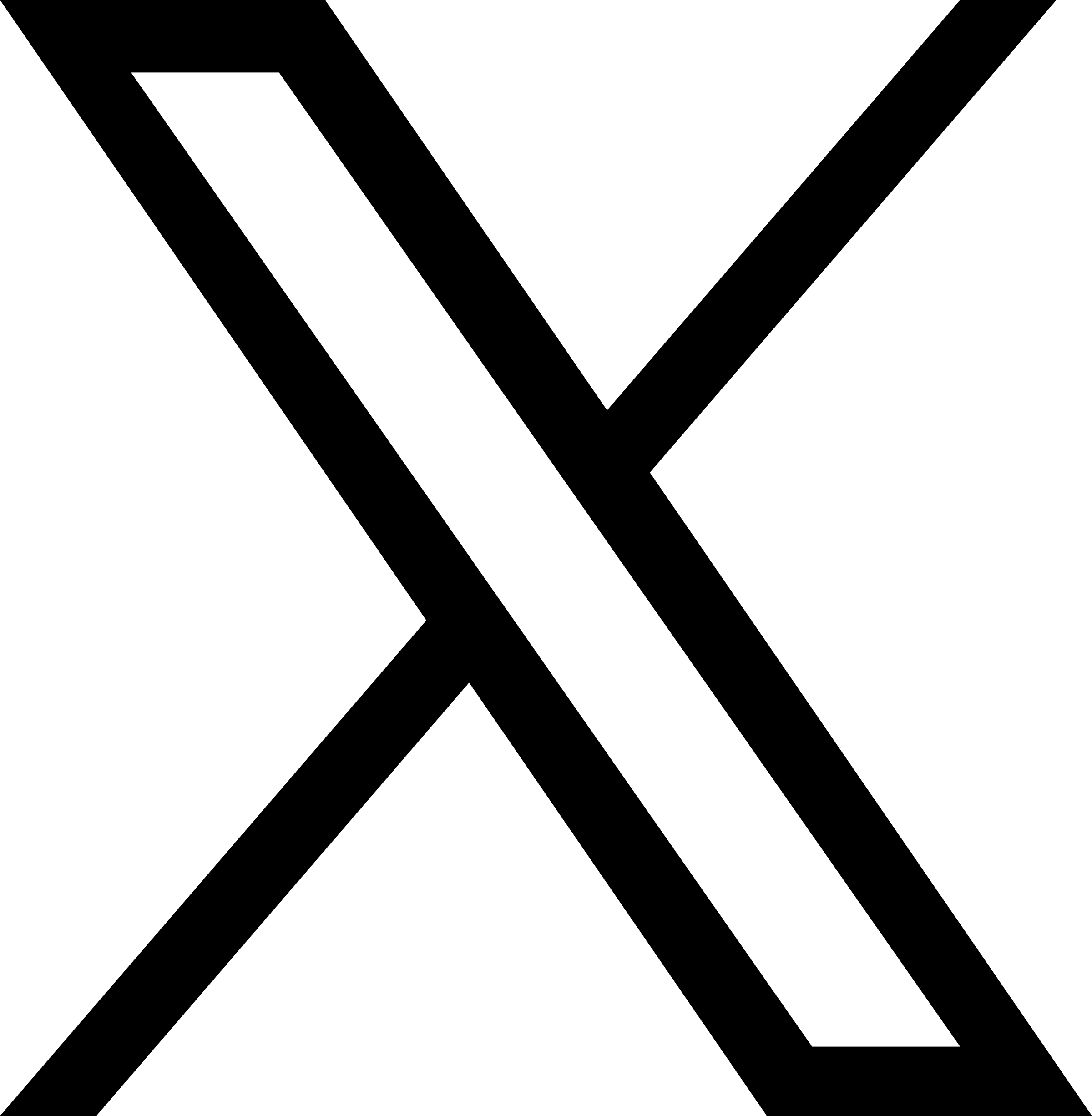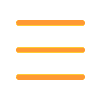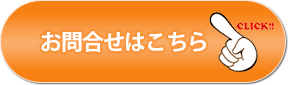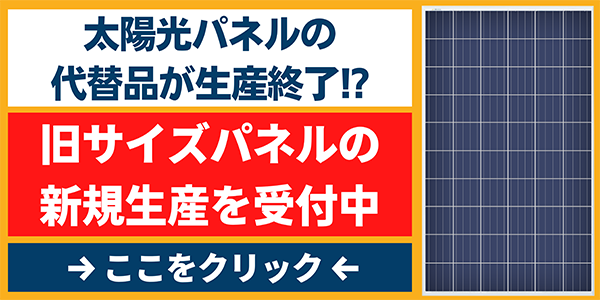目次
シリコン太陽電池とは?種類・最新技術と、EPCが押さえておきたい実務ポイント
日本国内で稼働している太陽光発電設備の大半は、シリコン太陽電池を使った発電所です。
FIT初期から大量に導入された設備は、今まさに「新設」だけでなく「リパワリング」「部分更新」のフェーズに入りつつあります。
同じシリコン太陽電池といっても、
- セル構造(PERC / TOPCon / HJT など)
- モジュールサイズ・機械的仕様
- 劣化特性・温度特性
によって、発電所の収益性や将来の更新のしやすさが大きく変わってきます。
ここでは、EPC・設計・施工に関わる方向けに、
「技術の基本」と「実務での判断軸」が両方つかめる視点で整理していきます。
1. シリコン太陽電池の基本と発電の仕組み
シリコン太陽電池は、シリコン半導体の pn 接合を利用して、光エネルギーを電気エネルギーに変換するデバイスです。
- p型シリコン層(正孔が多い側)
- n型シリコン層(電子が多い側)
- 両者の境目「pn接合」にできる電位の壁
- 表面電極・裏面電極
太陽光がセルに入射すると、シリコン内の電子が励起され、
pn 接合部でプラス側・マイナス側に分かれ、その電子の流れが電流になります。
この「セル」を直列・並列に接続したものがモジュールであり、
モジュールをさらにストリングとして束ね、パワコンに接続して発電所全体が構成されています。
2. 単結晶・多結晶・薄膜の違い
シリコン太陽電池は大きく以下に分類されます。
単結晶シリコン
- 規則正しく揃った結晶構造
- 変換効率が高く、黒っぽい外観で意匠性が高い
- 屋根上や敷地面積が限られる案件で採用しやすい
現在、日本市場で新設案件の主流はほぼ単結晶です。
多結晶シリコン
- さまざまな結晶が集まった構造
- コスト面で優位だったため、FIT初期には非常に多く採用
- 近年は単結晶の高効率化・低価格化が進み、採用は減少傾向
薄膜系シリコン・その他
- 軽量・大面積対応といった利点
- 出力・効率面では結晶系に比べて不利な部分も多く、
日本のメガソーラー市場では採用は限定的
現在は「どの材料にするか」よりも、
「どの世代の単結晶技術を使うか」が設計上のポイントになりつつあります。
3. PERC・TOPCon・HJT:セル技術の世代差
同じ単結晶モジュールでも、セル内部の構造・世代によって性能が変わります。
PERC(パーク:Passivated Emitter and Rear Cell)
- 裏面側にパッシベーション層(反射・保護層)を設けて光利用を高めた構造
- 従来のセル構造に比較的少ない変更で導入できるため、
2010年代後半〜2020年代前半の主力技術となった - コストと効率のバランスが良く、「一世代前の主流」としてまだ多く流通
TOPCon(トップコン:Tunnel Oxide Passivated Contact)
- n型シリコン基板をベースに、極薄酸化膜+パッシベーション層などを組み合わせた構造
- 電子が抜けるときのロスが少なく、長期的な劣化も抑えやすいと言われている
- PERCでは伸びしろが小さくなった「効率アップ」を、次のレベルに押し上げる存在
量産ラインを既存の PERC から比較的スムーズに移行できる点や、
長期発電量の高さから、世界的にTOPConへのシフトが加速しています。
HJT(ヘテロ接合:Heterojunction)
- 単結晶シリコン基板の上に、アモルファスシリコンを重ねるハイブリッド構造
- 変換効率・温度特性が非常に優秀で、低照度時の発電にも強い
- 製造プロセスが異なるため設備投資が大きく、パネル単価は高めになりがち
高効率・高付加価値を求める屋根上案件や、
LCOE(発電コスト)重視の長期案件で採用が進んでいます。
4. なぜ今「TOPCon」が主流になりつつあるのか?
近年、多くのモジュールメーカーが PERC から TOPCon へシフトしている背景には、
単純な効率向上だけでなく、量産性と長期信頼性のバランスがあります。
- PERC は成熟技術である一方、到達効率が頭打ちになりつつある
- TOPCon は PERC と大きく異なる「新素材」ではなく、既存ラインの延長で生産しやすい
- 高温環境下でも性能が落ちにくく、LeTID などの劣化リスク低減も期待できる
結果として、「少し高くても長期発電量が高い=LCOE を下げやすい」
という評価がなされやすくなり、世界的な主流技術へ移行しつつあります。
日本のように夏場のモジュール温度が高くなりやすい市場では、
この「長期的な安定発電」という視点は、特に投資家・金融機関からも注目されています。
5. シリコン原材料と価格変動リスク
シリコン太陽電池のコスト構造を見ると、
セル技術だけでなく「ポリシリコン(多結晶シリコンインゴットの原料)」の価格も重要です。
- 2021〜2023年ごろ、ポリシリコン価格急騰によりモジュール価格が一時上昇
- その後、生産能力の増強や供給過多により価格は下落・安定方向へ
今後もエネルギー価格や地政学リスク、環境規制などによる
価格変動リスクは完全には消えません。
EPC・施工会社としては、
「今いちばん安いメーカー」ではなく、
中長期的に調達・アフターサービスを継続できるサプライチェーンか
という視点も併せて確認しておくと安心です。
6. EPCがチェックしたい「実務指標」
① 温度係数
真夏の屋根上では、モジュール温度が 60℃ を超えることもあります。
セル技術により温度係数は異なり、同じ kW 数でも夏場の実発電量に差が出ます。
- 一般的な結晶シリコン:おおよそ -0.35〜-0.45%/℃
- HJT など一部技術:より温度係数が良く、夏場の出力低下が小さい
「システム全体のピーク発電量」だけでなく、
夏場の発電プロファイルまで含めて見るのがポイントです。
② モジュール大型化と架台・施工への影響
最近の大出力モジュールは、
- ウェハサイズ:156 → 166 → 182 → 210mm クラスへ大型化
- 1枚あたりの出力:300〜400W台 → 500〜600W台へ
と進化してきました。
メリット
- 使用枚数が減る → 配線・架台・統合コスト削減の余地
- 大規模案件での工事期間短縮
一方で、
- 1枚あたりの重量増加
- 風荷重・雪荷重への配慮
- ハンドリングの難易度アップ
など、施工現場にとっての負荷も忘れてはいけません。
「何Wのパネルか?」だけでなく、「1枚あたりのサイズと重量」が現場に合うかどうかが重要です。
③ リパワリング・部分交換時の互換性
既存設備の一部パネルだけを交換する場合は、
「出力」より先に、以下を確認する必要があります。
- 外形寸法(長さ・幅)
- フレーム厚
- 取付穴位置
- 接続コネクタの種類・定格電圧
- ストリング電圧との整合
ここを見逃すと、架台加工が必要になったり、
既存パネルとの電気的ミスマッチが発生したりしがちです。
7. シリコン太陽電池と「発電所の資産価値」
これまで太陽光発電は「20年間発電するインフラ」という見方が主流でしたが、
最近は「運用しながら資産価値を維持・再構築するインフラ」という考え方が広がりつつあります。
- 将来の第三者売却(セカンダリー取引)
- FIT 終了後の継続運用
- 部分的なパネル交換・パワコン更新
こうした「長い時間軸」で見たとき、
初期段階でどのシリコン太陽電池を採用するかは、
発電所の評価・売買価格・改修コストにまで影響してきます。
「安く買えたから OK」ではなく、
20〜30年のライフサイクル全体で見て合理的かどうか――
これが、これからのモジュール選定のスタンダードになっていきそうです。
8. 情報・製品をどう活かすか
シリコン太陽電池は成熟した技術のようでいて、
セル世代・モジュールサイズ・設計トレンドは今もアップデートが続いています。
- 既存発電所の一部更新
- FIT 初期案件のリパワリング
- 陸屋根・遊休地・営農型といった特殊条件の案件
といったテーマでは、
「どの世代のセル技術を、どの架台と組み合わせるか」まで含めて、検討が必要です。
ソーラーデポ運営元のUpsolar Japanでは、こうした実務課題に対して、
- 旧サイズパネルの互換確認・対応製品の提案
- 陸屋根向けアンカーレス架台「UP-Base NEO」
- 垂直型・営農型向け「UP-Stand」
- 設置条件に応じた製品選定のサポート
なども行っています。
具体的な案件で「この現場に最適なパネル・架台の組み合わせが知りたい」という方は、Upsolar Japanの技術資料やフォームからのご相談も参考にしてみてください。
参考文献・出典リスト
-
IEA PVPS Task 1
Trends in Photovoltaic Applications 2024
国際エネルギー機関 太陽光発電技術プログラム 年次レポート -
Fraunhofer ISE
Photovoltaics Report
欧州最大級の太陽光研究機関による技術・市場レポート -
ITRPV
International Technology Roadmap for Photovoltaics 2024
太陽電池技術ロードマップの国際標準的資料(PERC/TOPCon/HJT動向含む) -
NEDO(新エネルギー・産業技術総合開発機構)
『太陽光発電技術開発ロードマップ』
日本の太陽光発電技術の中長期戦略資料 -
経済産業省 資源エネルギー庁
『太陽光発電の現状と課題』
日本における導入状況・政策・市場動向 -
JPEA(一般社団法人 太陽光発電協会)
『太陽光発電設備の技術動向・市場動向に関する調査報告』 -
Green, M. A. et al.
Solar cell efficiency tables (Version 62, Progress in Photovoltaics)
世界の太陽電池変換効率の公式更新表 -
Luque, A. & Hegedus, S.
Handbook of Photovoltaic Science and Engineering
Wiley出版、太陽光発電の標準的専門書 -
JIS C 8907 / JIS C 8990
太陽電池モジュール性能評価および試験方法に関する日本工業規格 -
IEA Renewables 2023 / 2024 Report
IEAによる世界再生可能エネルギー市場動向