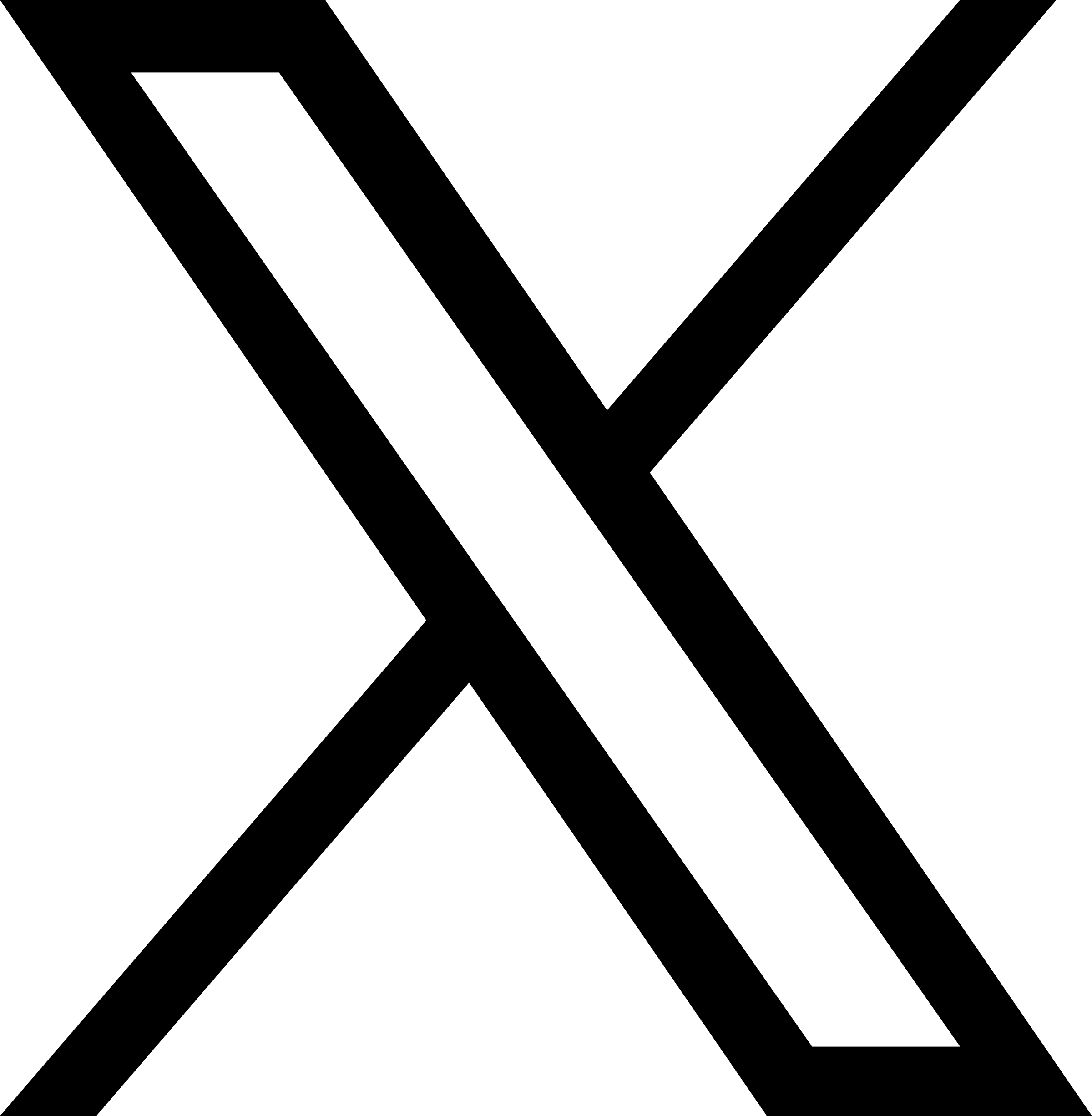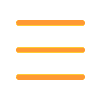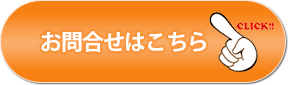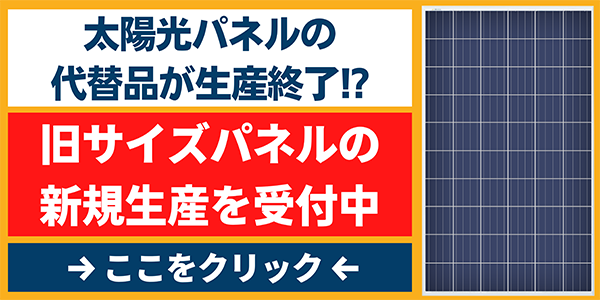2025年10月から、産業用太陽光発電(10〜50kW未満・屋根設置案件)における固定価格買取制度(FIT)が大きく変わりました。
従来の「20年間同一価格」から、前半5年間は高単価、後半15年間は低単価という二段階制度へ移行したのです。
この改定は、事業者・EPCにとって「売電モデルから自家消費モデルへ」の大きな転換点となります。
目次
改定後のFIT価格(2025年10月〜)
| 改定前 | 改定後(2025年10月以降認定) | |
|---|---|---|
| 産業用(10〜50kW未満・屋根) | 11.5円/kWh(20年間固定) | 1〜5年目:19円/kWh 6〜20年目:8.3円/kWh |
改定の背景
-
初期投資回収を早期化:前半に収益を集中させ、投資障壁を下げる狙い。
-
自家消費へのシフト:6年目以降は売電単価が低く、電気代削減効果の方が優位。
-
制度の持続性確保:長期高単価FITによる国民負担増を回避。
今後の見込み(2026年以降)
-
自家消費型が標準に
売電依存から「自家消費による電気代削減」へ完全移行。 -
PPA・自己託送の拡大
初期投資ゼロのPPA、複数拠点を結ぶ自己託送が広がる。 -
FIP制度への移行
市場価格連動のFIPが小規模案件にも適用される見通し。価格変動リスクを織り込んだ設計が必要。 -
蓄電池の普及
出力制御対策・ピークカットのため、太陽光+蓄電池の導入が一般化。 -
産業・公共案件における屋根設置の拡大
国・自治体が支援を強化。特に防水対応・アンカーレス架台の需要が高まる。
初期投資を軽くする方法
(1) 補助金の活用
-
省エネ補助金(中小企業庁):設備費の1/3を補助。LEDや空調とセットで採択率UP。
-
環境省「再エネ×蓄電池支援事業」:太陽光+蓄電池で最大1/2補助。
-
自治体補助金(東京都・大阪市など):産業・公共案件における屋根設置や蓄電池導入を重点支援。
(2) 税制優遇
-
中小企業経営強化税制:即時償却100%または10%税額控除。
-
グリーン投資減税(検討中):法人税控除の拡大が見込まれる。
(3) 金融スキーム
-
PPAモデル:初期投資ゼロ。利用者は電気を購入するだけ。
-
リース・ローン:投資を分割払いで平準化し、電気代削減効果でキャッシュフロー改善。
-
自己託送:複数拠点を結び、発電電力を自社内で融通。
(4) 組み合わせ戦略の例
-
補助金で300万円削減
-
税制で100万円軽減
-
残り600万円をリースで分割
⇒1,000万円規模の案件でも、実質初年度負担は数百万円以下に抑えることが可能。
制度変化を踏まえた製品選択のポイント
2025年以降の市場では、「初期投資を抑えながら自家消費を最大化できる設備」が求められます。
UP-Base NEO(アンカーレス陸屋根用)
-
防水層を傷つけないアンカーレス設計で、産業・公共案件における屋根設置に最適。
-
耐荷重40kg/m²対応で、多雪地域や強風地域でも安心。
-
補助金やPPAモデルと組み合わせることで、低負担での導入加速を実現。
UP-Stand(垂直太陽光架台)
-
農地や遊休地でも設置可能で、営農型ソーラーシェアリングに有効。
-
作物栽培と発電を両立し、農業×再エネモデルを実現。
-
FIT後半の低単価局面でも、自家消費や営農収益と組み合わせることで効果的。
まとめ
-
制度改定により、太陽光は「売電収益」から「自家消費+脱炭素」へ完全にシフト。
-
EPCは補助金・税制・金融スキームを組み合わせ、顧客の投資負担を下げる提案が求められる。
-
その上で、産業・公共案件ではUP-Base NEO、農地・遊休地ではUP-Standが有力な選択肢となる。
お問い合わせ
「自家消費型への転換」をどう進めるか迷われている方へ。現場に合わせた最適なご提案をお届けしますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
参考文献
-
-
経産省「調達価格等算定委員会資料」(2025年度FIT改定)
-
経産省「FIP制度運用方針」
-
環境省「再エネ導入支援・PPA普及資料」
-
中小企業庁「中小企業経営強化税制」
-
各電力会社「出力制御実績」
-
経産省「蓄電池産業戦略会議」報告書
-
東京都「地産地消型再エネ・蓄エネ補助金」2025年度概要
-
エネルギー基本計画(第6次、次期第7次検討中)
-